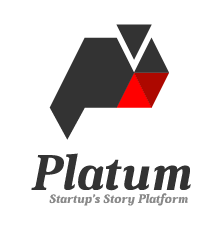起業支援はあふれているが、スタートアップがこぞって廃業する酷寒期の状況で「きちんと解散する方法」を見つけるのは難しかった。このような情報空白を埋める実務ガイドが登場した。スタートアップが廃業する時、創業者一人が全ての負担を負う構造的問題を解決するための実務マニュアルだ。
STARTUP ALLIANCE(スタートアップアライアンス)とAsan Nanum Foundation(アサンナヌム財団)が共同発刊した「スタートアップ解散ガイドブック」は「起業失敗と解散」を真正面から扱った。
Asan Nanum Foundationのチョン・ナミ常任理事は今回のガイドブック発刊の背景をこう説明した。 「創業初期には支援と情報が溢れているが、整理段階は漠然としている」とし、「解散することを中立的価値と見て、透明な手続きを踏まなければ信頼は維持されない」と強調した。
チョン氏は「廃業が製品を信じて使用した顧客、会社を成長させた社員、未来の可能性を見て投資した投資家ら、共に歩んできた人々に及ぼす影響を深く理解し、その過程に責任を持つことができたとき、初めて本当の意味で解散が可能になる」とし、「何よりも透明で信頼できる情報と手続きが必要だ」と付け加えた。
STARTUP ALLIANCEのイ・ギデ・センター長は「起業エコシステムは失敗と再挑戦まで包括してこそ持続可能となる」とし、「今回のガイドは単純な法律手続き書ではなく、崩れた後も生き残る方法を伝える生存マニュアルだ」と意義を強調した。

Asan Nanum Foundationのチョン・ナミ常任理事ⓒPlatum
「廃業は失敗ではなく、信頼を崩す過程です」。
ガイドブックの執筆に関わった法務法人ミッションのキム・ソンフン代表弁護士はスタートアップを解散する本質をこう定義した。 「株式会社は事業と資本が結合した高度な信頼システムだ」とし、「投資家と債権者、社員と顧客との信頼を安全に崩すことが解散の本質だ」と説明した。
キム氏は現実的な困難も指摘した。 「投資契約上、個々の同意権の構造がダウンラウンドと清算型M&Aを難しくする」とし、「普段の透明なコミュニケーションとガバナンスの整備が必要だ」と助言した。
キム氏は「スタートアップは基本的に高リスクの起業だ。当然失敗する確率が高い」とし、「信頼が崩れる過程を最大限安全かつ慎重に、信頼の基盤を損なわずに進めることが我々のエコシステムの課題だ」と強調した。
法的手続きの現実的な限界も浮き彫りとなった。キム弁護士は「スタートアップの更生は現金創出力が前提にならなければならないが、現実的には不可能だ」とし、「法人破産も予納金500万ウォン(約50万円)すらなくて申請できない場合が多い」と実情を打ち明けた。
Super Rabbit Games(スーパーラビットゲームズ)のキム・ヨンウン代表は廃業経験を率直に打ち明けた。 「一番難しかったのは事業停止することを自分が認めることだった」とし、「私が向かおうとする宝島への船に乗ることができず、泳いででも行きたかったが、ここで止まるしかないことを認めなければならなかった」と当時の心境を語った。
ゲーム開発者出身のキム代表は2013年にBEACON Studio(ビーコンスタジオ)を創業するも、7年後に廃業し、2023年にSuper Rabbit Gamesを再創業した。キム代表が再び起業に挑戦できたのは、最初の創業の解散をきちんと行ったからだと強調した。
「事業自体の問題ではなく、パートナー社から契約金15ヶ月分を受けられず、急激な財政悪化を経験した」とし、「廃業が事故のように襲ってきたが、投資家や社員たちに全ての経緯と手続きを透明にして共有した」と説明した。
キム代表は「事業を行った長い時間に、どのくらい危機感と期待感を共有したかが一番重要だった」とし、「廃業直前に一部残った社員たちと3~4つのプロジェクトを実験的に行ったが、それが次の起業の原動力になった」と付け加えた。
Dog mate(ドッグメイト)のイ・ハヨン前代表の証言はエコシステムの冷酷さを感じさせた。 「投資家に『潰れるなら早く潰れろ』と言われた時、エコシステムが失敗を人間的に扱わないということを感じた」とし、「廃業後には連帯保証が消えたとしても機関融資が妨げられるなど、2次被害が大きい」と訴えた。

STARTUP ALLIANCEのイ・ギデセンター長(モデレーター)、Translink Investmentのパク・ヒドク代表、Super Rabbit Gamesのキム・ヨンウン代表、Dog mateのイ・ハヨン前代表、法務法人ミッションのキム・ソンフン代表弁護士ⓒPlatum
Translink Investment(トランスリンクインベストメント)のパク・ヒドク代表は、投資家の観点から、解散をきちんと行ってこそ次の起業で成功できるという点に共感した。Kurly(カーリー)の初期投資家としても知られるパク代表は「(ベンチャーキャピタルとして)一度で成功した創業者もすばらしいが、失敗を重ねた中で成功した創業者はもっと認める」とし、「成功と失敗が重要なのではなく、その過程で何を学び、次にどのような起業をするのかが重要だ」と話した。
一方、パク氏は構造的限界も指摘した。 「韓国は債権者と投資家、社員の利害が絡み合い、創業者一人で調整することが難しい」とし、「普段のグラウンドルールを定めておかなければ危機に陥った時の対立がより大きくなる」と助言した。
韓国のスタートアップエコシステムは大きく発展したが、廃業する時は創業者たちが丸ごと負わなければならない負担が多いという構造的問題が依然として残っているとの指摘が出された。
キム・ソンフン弁護士は「法体系の中で一番先に社員との関係を考慮し、次に顧客と株主を考えなければならない」とする一方、「現実は投資家や株主の意思決定が優先される場合が多い」と指摘した。
キム氏は「投資家に求められ、無理に会社を維持して整理できない場合が多い」とし、「そうなると結果的に被害が大きくなる」と懸念を示した。
特に「結局、創業者が信用不良者になり、5年程度は経済エコシステムから退出する問題を解決しなければならない」と強調した。
イ・ギデ・センター長も「2015年だけでも教育部や中小ベンチャー企業部(部は省に相当)などで起業を奨励したが、景気が悪くなり、結果が悪ければ結局、被害を被るのは創業者だった」と韓国のスタートアップエコシステムの限界を指摘した。
キム・ソンフン弁護士は政策的改善策も提示した。 「政策金融とファンド・オブ・ファンズなど公的LPが監査リスクを避けようと過度な制裁を加える場合が多い」とし、「失敗を断罪するよりも、再挑戦を可能にするガイドラインが必要だ」と提言した。
キム氏は「背任や横領などの逸脱行為は厳しく責任が問われ、結果的失敗は容認すべきだ」とし、「創業者が再挑戦できる、弾力ある制度的回復の仕組みを作ってこそ、革新の土壌が持続する」と強調した。
法務法人ミッションのキム・ソンフン代表弁護士ⓒPlatum
今回公開された「スタートアップ解散ガイドブック」は、解散前の点検リストと手続き別の詳細な案内、投資家・社員・顧客ら利害関係者への対応ガイド、清算・破産・更生の違いと清算型M&A戦略などを総合的に盛り込んだ。
ガイドブックでは、特に創業者の意志による自律的解散手続きを具体的に提示した。解散を決めた創業者が踏まなければならない段階を創業者個人としての準備、家族との合意、知人及びメンターとの相談、会社としての手続きの4段階に分けて説明している。
会社レベルでは、各種公的資金の返済から始まり、社員の退職金と賃金処理、顧客対応、投資家との協議の順で進めるよう勧告した。特に「サービス中断案内とデータ移管」、「未処理業務の引き継ぎ」、「事務用品と資産の整理」など、実務担当者が見逃しやすいことを詳細に解説し、チェックリスト化した。
法と税務手続きだけでなく、賃金・退職金支給と顧客返金・データ移転、債権者協議など、現場で行われる現実的問題に対する具体的なアドバイスをまとめた点も特徴的だ。
Asan Nanum Foundationのチェ・ユニ経営本部長は「廃業は終わりではなく、もう一つの挑戦の基盤になり得る」とし、「今回のガイドブックが創業者の試行錯誤を減らし、次の跳躍を準備する道しるべになることを願う」と話した。
Asan Nanum Foundationのチョン・ナミ常任理事も「廃業は文字通り、ただ事業をやめるという意味だが、我々はこれをよく失敗や没落とつなげて受け入れる」とし、「企業が生まれ成長し、市場の変化の中で門を閉じるのは自然な循環過程の一部になり得る」と強調した。チョン氏は「今後は挑戦だけでなく、解散もまた尊重され、喝采される社会になることを期待している」と付け加えた。

ⓒPlatum
この日の懇談会はスタートアップエコシステムがこれまでタブー視してきた「失敗」と「解散」を真正面から扱い、健全な再挑戦文化づくりの必要性を掘り起こした。創業者の率直な経験談と専門家たちの政策提言が会場で議論され、失敗に対する烙印(らくいん)を消して再起の機会を拡大しようとする、エコシステムの意志を確認することができた。
<画像=2日、韓国・ソウル江南区のMARU 180で開かれた「スタートアップ解散ガイドブック発刊記者懇談会」の様子ⓒPlatum>