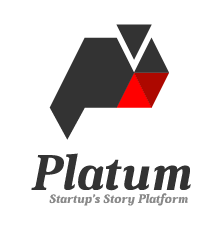2022年に開かれたイベント「アジアの韓国人」でDALCOMSOFT(タルコムソフト)のチェ・デホン日本支社長はこう話した。 「日本は計画にあったことは早く進めるが、計画になく、マニュアルがなければ几帳面に確認して進める傾向がある。事業計画を立てるとき、韓国で3ヶ月かかることが、日本では6ヶ月以上かかった」。
彼は具体的な事例を聞いた。 「我々は著作権などの問題がそうだった。日本では、アーティストの音源でゲームがリリースされたことがなかったため、どのように売上が出て決済されるかを理解させなければならなかった」。
この言葉は日本進出の本質を表している。マニュアルがない状況での徹底した検証、先例がないときの慎重さ。日本は韓国とは異なる、ルールに立ち返るゲームフィールドだ。
韓国輸出入銀行の統計を見ると、毎年平均176社の韓国企業が日本に法人を設立している。2024年だけで231社あった。しかし、定着に成功した企業は数えるほどだ。計算してみると、成功率は0.5%に過ぎない。
STARTUP ALLIANCE(スタートアップアライアンス)とWanted(ワンテッド)が日本進出企業44社を調査した結果はさらに示唆点が多い。75%が「市場の類似性」のため日本行きを決心したが、現地で最も大きな困難は「関係形成」(59.1%)だった。近いと思っていたものが、最も遠いものだったという逆説だ。
それでも成功した企業はある。これらの事例を分析すると、3つのはっきりしたパターンが見られる。
変身の技術:Channel Talk(チャンネルトーク)はオフライン分析ツールからオンラインチャットサービスに、カンナムオンニはヘルスケアアプリから美容プラットフォームに変身した。日本では固執より柔軟性が生存戦略だ。
隙間の発見:日本のインフルエンサーたちは、オフライン中心だという点を掘り下げてEコマース進出を助けた。KAFLIX(カフリックス)は皆が東京を狙う時、沖縄から始め、自治体の協力を引き出した。
現地パートナー:TimeTree(タイムツリー)はKakao(カカオ)ジャパン出身者が、Allganize(アルガナイズ)はヤフージャパン経験者が最初から合流した。BEAR ROBOTICS(ベアロボティクス)は初めからソフトバンクとタッグを組んだ。一人では迷路を乗り越えられないということを、いち早く悟ったのだ。
日本では「3年耐えなければならない」という言葉がある。これは単なる格言ではなく、市場の特性からくる必然だ。
日本の消費者は新しいサービスを受け入れるのに時間がかかる。しかし、一度受け入れれば忠誠度が高い。韓国のように6ヶ月で離れていかない。問題はその3年を耐えられる企業が多くないという点だ。
特に投資家の説得が難しい。「3年後に成果が出るでしょう」という言葉で投資を受けることは現実的に不可能だ。我々はみんな早く結果を出すことに中毒になってているからだ。
では、どうすれば良いのか?成功事例には共通する3つのカギがある。
まず、金を3倍準備せよ。単に運営費だけではない。高い人件費(ヘッドハンティング手数料だけで35-40%)、長いセールスサイクル、予想より長くかかる試行錯誤まで、全てが韓国の3倍だ。
第2に、現地ガイドを確保せよ。韓国人を派遣するよりも、現地の経験者を探す方が良い。日本企業の信頼を得るには、現地で長年の経験を積んだ人材が不可欠だ。コストはかかるが、ゲームのルールを知るプレイヤーがいると勝率が高くなる。
第3に、組織全体で覚悟を決めよ。投資家でも社員でも皆が韓国式のスピードを期待すれば、結局、皆が疲れる。 「少なくとも3年は耐える」という全社的な意志がなければ始めるな。
これらは全て難しいが、それでも日本はまだ魅力的だ。1億2千万人の巨大な市場、政府主導のDX政策、比較的開かれたIPO市場。何よりも、成功すれば安定した収益が保証される。
カギはスピードではなく、持久力のゲームだという点を認めることだ。韓国式の「早く、早く」では、日本という異なるゲームフィールドで勝てない。しかし、十分な準備と現地パートナー、そして長期的な視点があれば、ゲームのルールに慣れて勝利することができる。
毎年200社余りの企業が日本行きの飛行機に乗り込むが、成功するのは0.5%だけだ。残りの99.5%が失敗する理由を正確に知り、異なるゲームフィールドのルールを予め熟知していれば、その0.5%に属することができるだろう。