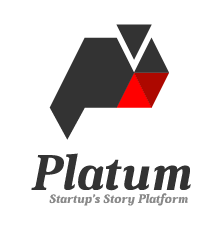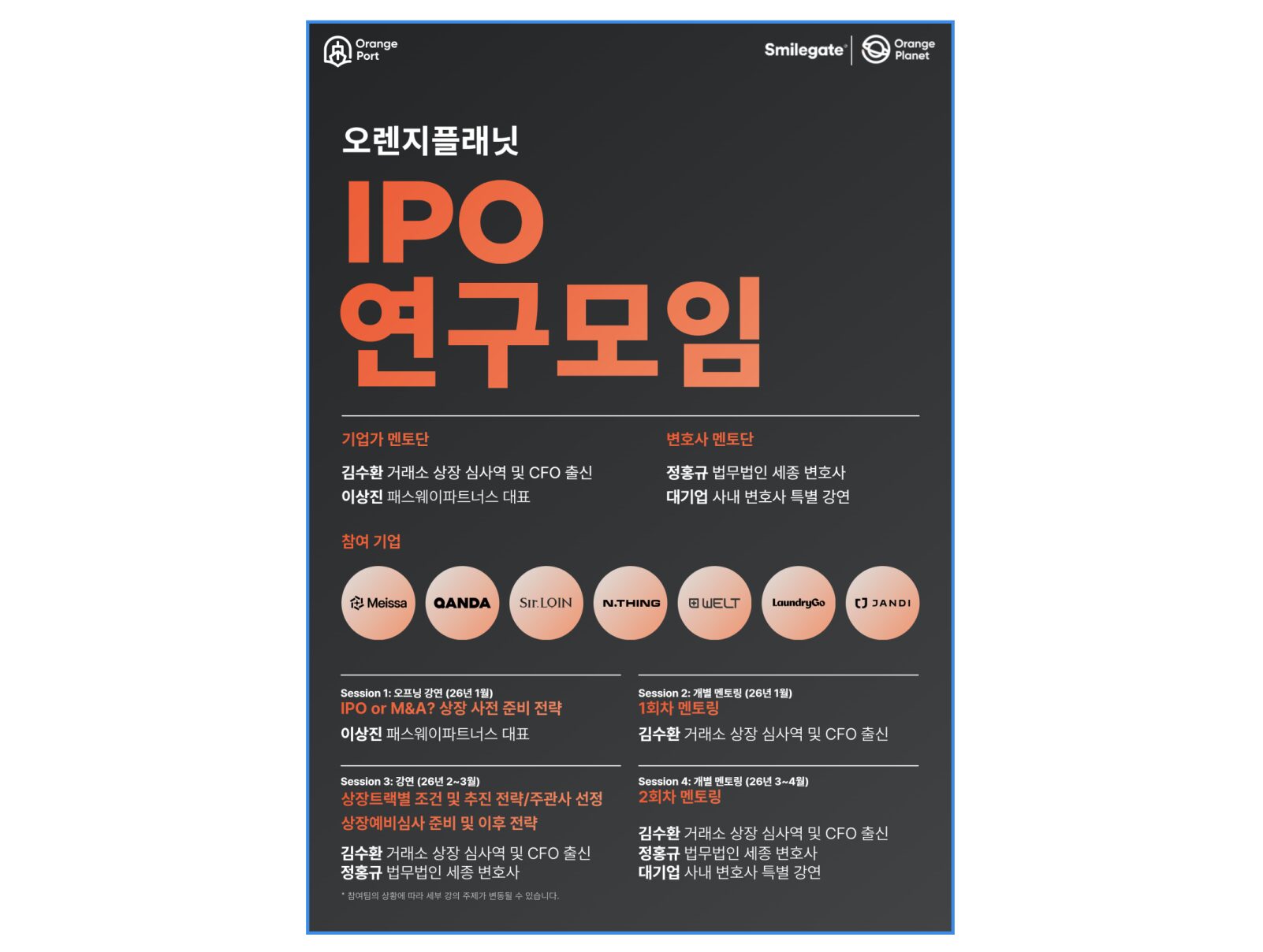目次
公共財源依存から脱皮、民間主導共生モデル拡大… 「直接投資して共に収益分け合う仕組みが核心」
地方消滅の危機、新たな解法登場
韓国社会が直面している地方消滅と地域経済の低迷の問題に、スタートアップが新しい解法を提示している。既存の公共財源投入やワンタイム開発方式を越えて、民間が主導し、地域住民が直接参加する持続可能な共生モデルが注目されている。
消滅危機にあった地域は、遊休不動産の増加、人口減少、産業空白という三重苦に苦しんでいる。このような状況でスタートアップは地域資産に直接投資し、定住環境を改善。地域ベースのコミュニティを構築し、人中心のエコシステムを復元する方向にアプローチしている。実際に人が流入して滞在する構造的変化を生み出しているという点で、期待感が高まっている。
Lucent block(ルーセントブロック)、地域住民参加型の不動産投資で好循環構造を構築
韓国中部の大田(テジョン)を基盤とするフィンテックスタートアップLucent block(ルーセントブロック)は、少額不動産のパーツ投資プラットフォーム「SOU(ソユ)」を通じて、地域共生のための革新的なモデルを提示している。市民が共同で当該地域の不動産に投資し、運営収益と売却収益を共に分け合う方式で、地域ベースの好循環投資構造をつくっている。
このモデルの成功事例としては、2022年末に公募した3号資産「大田起業スペース」が代表的だ。若い起業家のための共有オフィスとして運営され、年5%台の配当収益を着実に提供してきたこのプロジェクトは、最近、収益者総会での投票を通じて約15%の最終収益率で売却が確定した。特に、投資したのは全体の約60%が大田市民で、投資から運営、売却まで地域住民が直接参加して収益を得た模範事例として評価されている。
Lucent blockのこのような成果は今年3月、ハナ銀行との協力プロジェクトでも続いた。大田市の儒城(ユソン)区弓洞(クンドン)にある「大田ハナスタートアップパーク」公募プロジェクトは、ハナ銀行が地域の起業エコシステムの活性化を目標に大田市、Lucent blockとともに推進した事業で、年9%の配当収益が提供される。これは既存の金融商品に比べてかなり高いレベルで、地域投資の魅力度を大きく高めている。
Lucent blockの関係者は「地域住民が投資段階から運営、売却まで全プロセスに参加できる構造を拡大し続けていく計画だ」とし、「このような方式こそ、真の地域共生の基盤になれる」と話した。

BLANKの遊休ハウス
BLANK、遊休スペースの再生で地方消滅に対応
空間再生専門スタートアップBLANK(ブランク)は、遊休スペースを地域住民のための拠点に転換し、地域再生と人口消滅の問題解決に積極的に乗り出している。ソウルでは遊休スペースや商店街を活用してコワーキングスペース、コミュニティ空間、ウイスキーバーで構成された「空集合」を運営し、試験的な空間モデルを披露した。
さらに注目すべきは、BLANKが2021年から展開している地方都市プロジェクトだ。人口減少が深化している栄州(ヨンジュ)、安東(アンドン)、南海(ナメ)、束草(ソクチョ)、丹陽(タニャン)、麗水(ヨス)、済州(チェジュ)の7都市を中心に、放置された空き家を直接エイモデリングして賃貸及び運営する「遊休ハウス」プロジェクトを運営中だ。
このプロジェクトの核心は、単純なスペース提供を越えて、地域の定住環境の改善と新しい人口流入のための基盤づくりにある。BLANKは、空き家を買い入れたり賃借した後、現代的な住宅空間に変え、都心部に住む人たちの地方移住やワーケーションの需要を吸収している。この過程で、地域の建設業者やインテリア企業などとの協力を通じて、地域経済の活性化にも貢献している。
BLANK側は「遊休スペースの再生は物理的環境改善を越えて、地域の新たな可能性を示す象徴的意味合いが大きい」とし、「1ヶ所ずつ変化させていくと、地域全体の雰囲気と認識が変わる効果が得られる」と説明した。

Mangrove済州シティ
Mangrove、コリビングで新しいライフスタイルを提案
MGRV(エムジーアールブイ)のニューリービングコミュニティ「Mangrove(マングローブ)」は、様々な形態の共同体住居を通じて地域の活性化に貢献している。「Live」、「Stay」、「Work&Stay」の3種類のコミュニティを運営し、変化する住居トレンドと地域再生をつなぐ独特なモデルを提示している。
「Live」は様々な人々と調和して生きるコリビングハウスで、単身世帯の増加とコミュニティの回復に対するニーズを同時に満たしている。「Stay」は自分の家のように滞在し、日常を興味深く探求できる短期滞在空間で、観光と日常の境界をなくす新しい旅行文化を提案している。「Work&Stay」は、仕事と旅行が共存するリモートワークライフスタイル空間で、コロナ禍以降に広がった在宅勤務文化とワーケーションのトレンドを積極的に活用している。
中でも、済州で運営するMangrove済州シティは代表的な成功事例に挙げられる。1980年代に建てられた観光ホテルを改装した7階建ての建物で、仕事と休息のための90室のプライベート空間と、タプドン海岸の景色を眺めることができる共用スペースで構成されている。
特にこのプロジェクトは、地域資産の再活用と新しいライフスタイルの需要を効果的に組み合わせた事例として評価されている。老朽化した観光施設を現代的な感覚で再び生まれ変わらせ、ワーケーション需要層の流入を通じた地域のONE都心の活性化に実質的に貢献しているからだ。
現在、Mangroveはソウルの崇仁(スンイン)、新設洞(シンソルドン)、東大門(トンデムン)、新村(シンチョン)と江原高城(カンウォンコソン)、済州(チェジュ)市の6カ所で運営しており、各地域の特性に合った差別化したサービスを提供している。
成功要因は「地域住民の参加」と「持続可能性」
これらのスタートアップの共通点は、一方的な開発や投資ではなく、地域住民の積極的な参加に基づいている点だ。Lucent blockは、地域住民が直接投資家となって収益を共有する仕組みを作り、BLANKは地域企業との協力を通じて共生効果を創出している。Mangroveも地域の既存資産を活用しながら新たな需要層を流入させる方式でアプローチしている。
また、これらのモデルの核心は持続可能性にある。単発性イベントや一過性の投資ではなく、持続的な収益創出と再投資が可能な構造をつくり、長期的な地域発展基盤を設けている点が既存の地域開発方式との差別点だ。
業界関係者は「過去の地域開発が公共財源に依存したトップダウン方式であったならば、今は民間の創造的アイデアと地域住民の参加を基盤としたボトムアップ方式がより効果的であることが立証されている」と評価した。
政府も民間主導の地域再生に注目
政府もこのような民間主導の地域再生モデルに注目している。国土交通部(省)は最近、「都市再生ニューディール事業」で民間の参加を拡大する方向に政策を修正し、中小ベンチャー企業部(省)も「地域特化起業支援プログラム」を通じて地域ベースのスタートアップ育成に積極的に乗り出している。
また、各地方自治体も遊休不動産の情報提供、規制緩和、税制優遇などを通じて、こうした民間主導のプロジェクトを支援する政策を相次いで打ち出している。大田市のケースでは、Lucent blockとの協力を通じて「市民参加型都市再生モデル」を他の地域に拡大させる計画を立てている。
しかし、これらのモデルを全国的に広げるためには、まだ解決しなければならない課題がある。何よりも、初期投資資本の確保の難しさと地域ごとの特性に合ったカスタムモデルの開発の必要性が指摘されている。
また、法制度の整備も急務だ。少額不動産投資に関する規制、遊休不動産の活用による各種認可手続き、コリビングなど新しい住宅形態に対する制度的サポートなどが改善されてこそ、より多くのスタートアップがこの分野に進出できるだろう。
専門家らは、こうした民間主導の地域再生モデルが今後、韓国の地方消滅問題の解決に重要な役割を果たすと見ている。特に、MZ世代の価値観の変化とコロナ禍以降拡大した遠隔勤務文化などが、このようなトレンドをさらに加速させると予想される。
業界の別の関係者は「単純に地域のインフラ構築にとどまるのではなく、直接的な投資をはじめ、人が戻って定住できる理由をつくることが重要になった」とし、「地域内の不動産と人口が好循環する持続可能なモデルに対する関心が今後も高まり続けるだろう」と見通した。
地域再生の新たなパラダイム
結局、スタートアップが提示する地域再生モデルの核心は「人」だ。物理的環境の改善を越えて、人々が集まり、留まり、再び投資したくなる好循環構造をつくるのだ。これは既存の官が主導する開発方式では限界があった部分で、民間の創造性と市場の効率性が結合した新しいアプローチ法といえる。
今後、より多くのスタートアップがこの分野に進出し、成功事例が蓄積され、韓国型地域再生モデルがさらに洗練されることが期待される。地方消滅という危機を機会に変えるスタートアップのイノベーションが、果たしてどのように実を結ぶのか、成り行きが注目される。