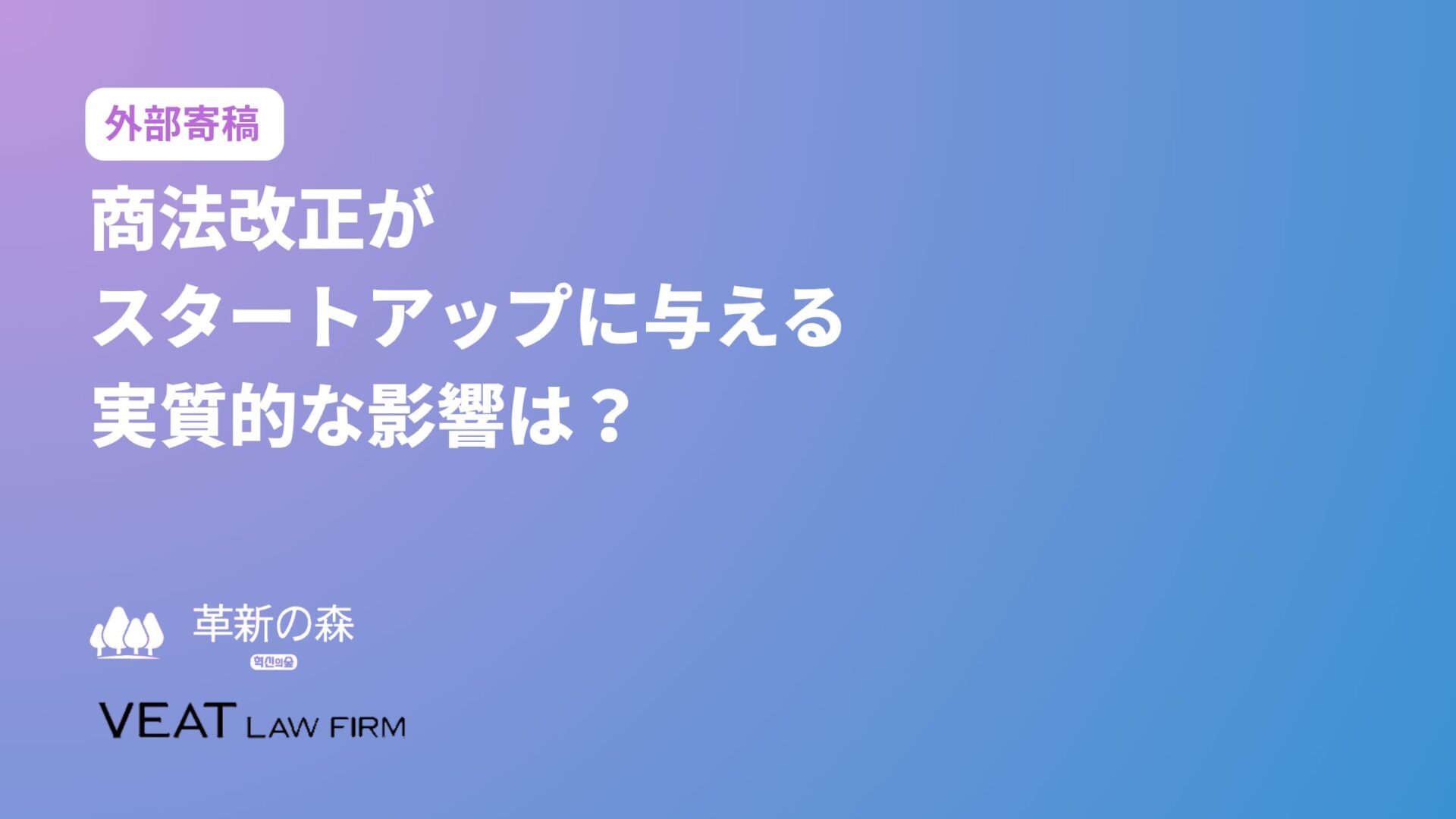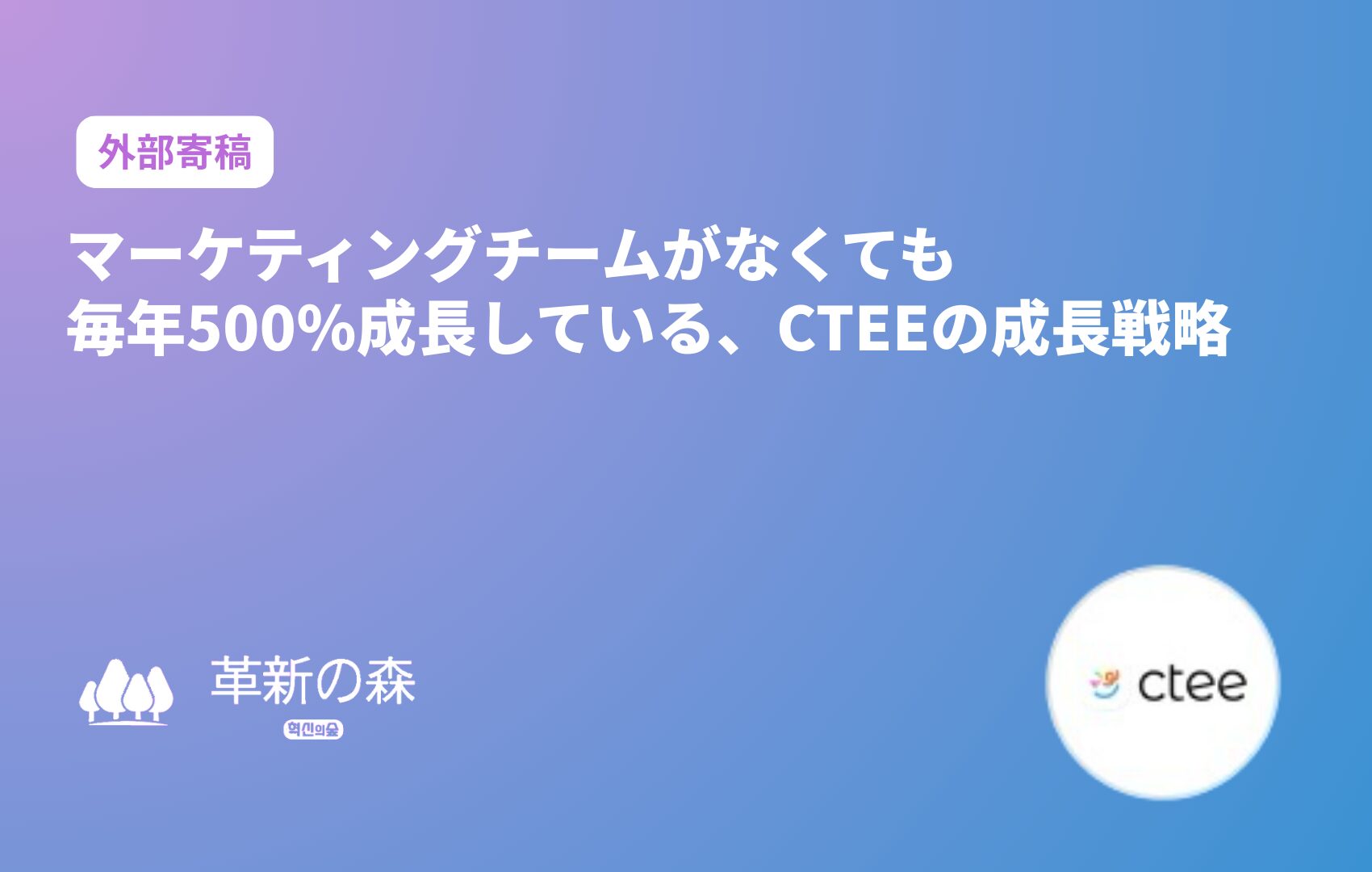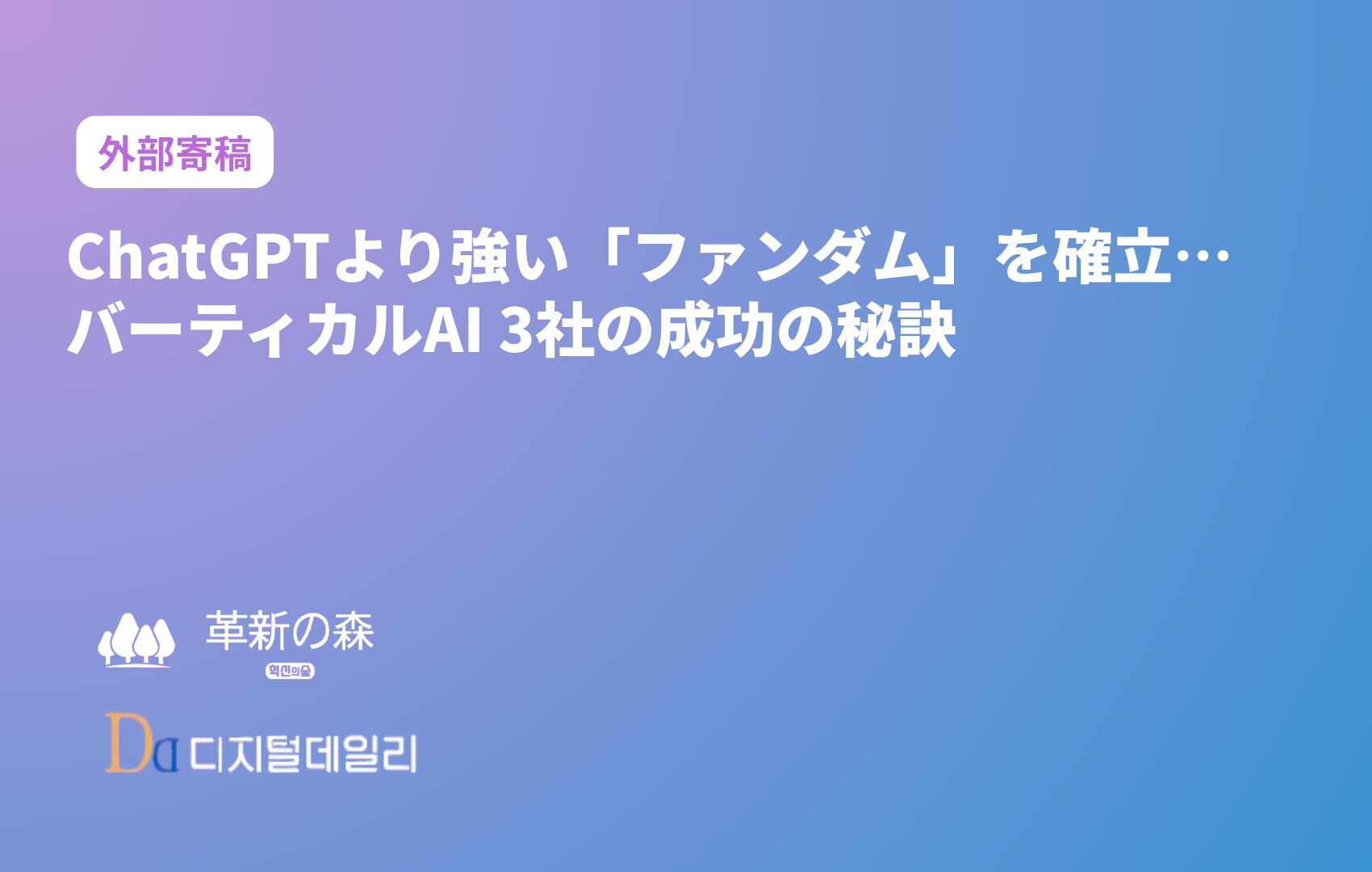7月22日に国会通過した商法改正案、うちの会社にも影響を及ぼすの?
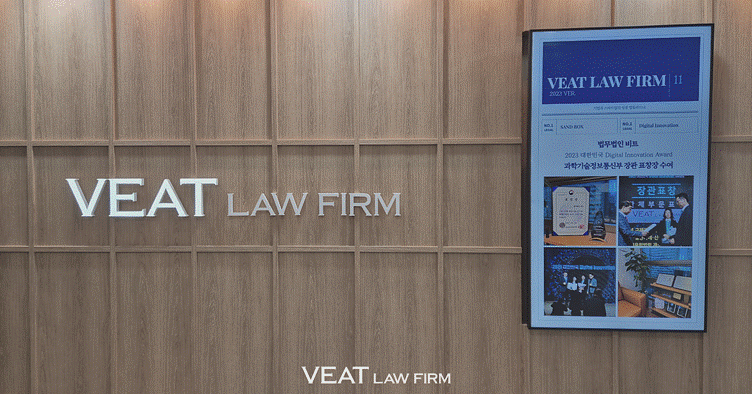
7月22日、国会を通過した商法改正案は韓国企業の支配構造に、大きな変化をもたらすと予想されます。
今回の改正案の核心は△取締役の充実義務対象を株主まで拡大 △上場会社の電子株主総会の導入 △上場会社の社外取締役名称変更及び選任比率の上方 △監査委員選任時の最大株主の議決権3%制限などで、全体的に株主権益保護に焦点が合わせられています。
上場会社中心の規定は現在、大多数のスタートアップには直接適用されてはいませんが、「理事の充実義務の拡大」は非上場会社にも同様に適用されます。スタートアップの取締役の多くが起業家であり主株主であることを考慮すると、起業家にも改正商法に基づく新たな責任が発生する可能性があります。今回の改正がスタートアップに与える示唆点と起業家・経営陣・投資者に及ぼす具体的な影響を見ていきます。
取締役の充実義務の拡大
これまでの商法第382条の3では「取締役は法令と定款により会社のためにその職務を忠実に遂行しなければならない」と規定し、充実義務対象を「会社」に限定しました。つまり、理事は会社の成長と運営に忠実でなければならず、その他の者まで考慮する義務はありませんでした。 (ここで「取締役」とは登記理事を意味するため、役職のみ「取締役」で、登記されていない者は該当しません。)
一方、改正商法第382条の3第1項はこれを「取締役は法令及び定款の規定により会社及び株主のためにその職務を忠実に遂行しなければならない」に変更され、第2項では「取締役はその職務を遂行するに当たって総株主の利益を保護しなければならず、全体株主の利益について公平に対応しなければならない。」と明示しています。
変更された事項をまとめると、最初の充実義務の対象が「会社」から「会社および株主」に拡大されました。第二株主に対する充実義務の内容が「総株主の利益保護」と「全体株主の公平な待遇」に具体化されました。その結果、個々の取締役個人が負担する責任の範囲が実質的に広がりました。

株主に対する損害賠償責任
一方、これまでの商法では取締役の損害賠償責任について、「第三者」に対する責任を規定しています。これは、取締役が会社の業務をきちんと行わず、会社の取引相手や債権者に損害を与えた場合、個人的に賠償しなくてはならない可能性があるということを意味します。例えば、経営状態が悪化して製品生産が不可能なA社の取締役がこれを隠し、B社と物品供給契約を締結し、前金を受け取った後、供給しなかった場合、A社だけでなく該当取締役もB社に個人的に損害賠償責任を負います。
ただし、最高裁判所は、このような損害賠償の対象である「第三者」に対して会社債権者や取引相手方は含まれるが、会社損害による株主の経済的損失は間接損害とみなして株主に対する直接的損害賠償責任は認めないという立場をとってきました。(最高裁判所2003.10.24.宣告2003ダ29661判決を参照)。つまり、取締役の意思決定は会社の利益に向いていたが、少数株主の利益は侵害されたという場合、これを法的に争うことは困難でした。
法令の「株主に対する充実義務」が明示されたことにより、既存の判例法は修正される可能性が高いです。取締役が会社の利益には合っているものの、多数株主に損害となる意思決定をした場合、株主に対する個人的損害賠償が生じる可能性が高まりました。このような意思決定の代表的な事例としては、会社事業部分割後の子会社別途上場、合併時の不公正な合併比率の適用、特定株主を対象とした有償増資や自社株買いなどが挙げられます。

起業者に適用される新しい忠実義務
取締役の充実義務の拡大は、スタートアップの起業者や経営者にも直接影響を及ぼす可能性があります。ほとんどのスタートアップが株式会社の形をとっており、起業者が登記取締役として経営の最前線に立っているためです。スタートアップにも起業者、投資家、個人株主など様々な利害関係の株主が存在するため、スタートアップの取締役も充実義務拡大の影響を受けざるを得ない。
たとえば、経営陣の故意または重過失で会社が損害を受け、その結果会社の株価が低下するというケースで想定すると、当該の取締役は、従来は会社に対してのみ損害を賠償すればよかったのが、今回株主(投資家)にも損害を賠償する可能性が生じました。スタートアップなどの非上場企業は株価評価が難しいですが、法的観点から見ると、最近の取引価格や投資価値に基づいて株価の下落を計算し損害を算定することは不可能ではありません。
また、スタートアップでも合併、分割、営業譲渡、新規資金調達など会社の構造変更は頻繁に起こります。この過程で株主間の見解がすれ違い、特定の株主が損害を受けるというケースは少なくありませんが、このような状況においても拡張された取締役の充実義務は適用されます。特に、経営陣が合理的な理由なく特定の株主または投資家に有利な投資条件を適用し、他の株主の持分を不当に希釈したり株価を落としたりした場合、株主に対する充実義務違反という評価を受ける余地があります。
一般に、ほとんどのスタートアップ投資契約書には、後続投資を低い企業価値へと導くこと(いわゆる「ダウンバリュー」または「ダウンラウンド」)を禁止する条項があるため、投資家は商法改正案の内容が適用されなくても会社の新株発行による直接的損害からある程度保護されることがあります。しかし、単なる企業価値の問題を超え、より多くの株主権や優越的投資条件を提供する場合、やはり「全体株主の利益を公平に扱う」ことをしていないと判断される余地が新たに生じたのです。
一方、会社の生存のためにやむを得ずダウンラウンドを進めるというケースも存在するでしょう。この場合、多くの投資家が市場環境を考慮して「ダウンラウンド」に同意していても、一部の株主は依然として「全株主利益の公平な扱い」を主張する可能性があります。この状況では、取締役が個人的な責任を負い、投資を継続するのは難しくなることもあるでしょう。
その他非常勤取締役の役割
こうした取締役の義務は、登記されたすべての取締役たちに同様に適用されるため、投資会社またはVCが投資プロセスで任命するその他の非常勤取締役にも同様に適用されます。これにより、投資家が選任したその他非常勤取締役の役割にも変化が起きると予想されます。
複数の取締役が取締役会で議決した事案で株主に損害が発生した場合、当該案件に賛成した取締役が責任を負うため、株主に損害が発生する可能性のある案件では、投資家が任命したその他の非常勤取締役は、小さなリスクでも反対票を投じる可能性が高くなります。
これは、起業者である取締役にとっては、資本構造の変更や構造変更などの重大な事案で迅速な意思決定を難しくする難点として作用することがありますが、投資家の立場としては、自分が任命したその他の非常勤取締役が取締会に積極的に参加して株主の利益を代弁することが期待できます。

まとめ
起業者であり主株主が会社を直接経営する取締役となるスタートアップの特性上、取締役の拡張された充実義務はスタートアップ経営全般に少なからぬ影響を及ぼすと予想されます。
ただし、今はまだ商法改正案が施行(7月22日)されてから2週間であるため、取締役の充実義務の拡大に関する解釈基準が確立、十分な事例が蓄積されるまでは、具体的にどの事例で取締役がどの程度の責任を負うことになるか判断するのは難しいです。
現在の時点でスタートアップ、特に会社の登記取締役である起業者は、合併、分割、第三者の新株発行(資金調達)、経営権紛争などの利害衝突の可能性が高い取引をしたり、会社の株価を下げる副作用が予想できる意思決定をする際には、注意の必要があります。こうした意思決定が他の株主の利益を侵害する可能性があるかどうかについて実質的に検討する必要があります。
一部の株主の利益侵害が避けられないと判断される場合、その不利益を最小化・補完できる方案を設け、一連の過程が合理的経営判断として株主利益を侵害していないことを裏付ける根拠資料を残す必要があります。
今回の商法改正はスタートアップエコシステムに新たな責任と義務を課しますが、同時に投資家保護と企業支配構造改善という肯定的な効果も期待されます。起業家と投資家の両方が変化した法的環境を理解し、それに合った意思決定を下し、重要な決定を控える際には、取締役の充実義務違反がないかを慎重にチェックする過程を経る必要があるでしょう。

原文:https://www.innoforest.co.kr/report/NS00000399
革新の森:https://www.innoforest.co.kr/
マークアンドカンパニー:https://markncompany.co.kr/