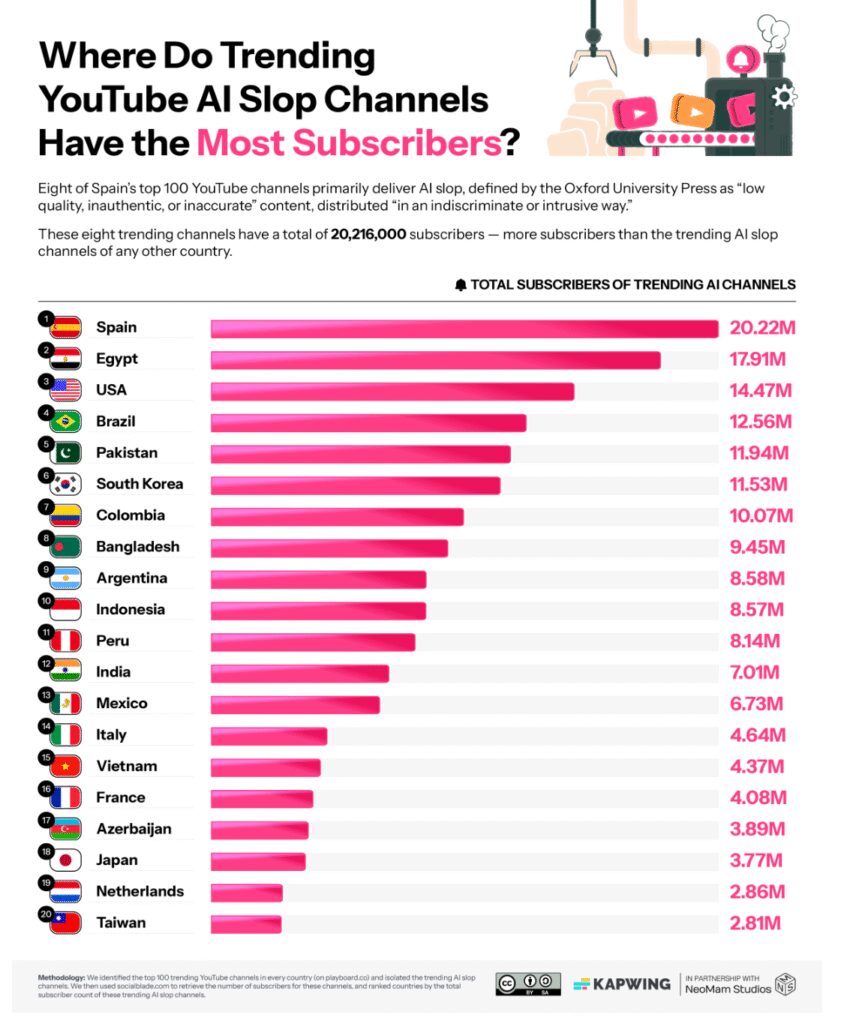ドラマシリーズなどを無断で要約・編集した「ファスト映画」を対象とした法的対応の動きが本格化している。著作権を侵害しているとみられるファスト映画が確認されている主要プラットフォームのYouTube(ユーチューブ)に対しても、規制の必要性が提起されている。
15日、業界によると、CJ ENMをはじめとする多くの韓国の放送局と映画制作会社が、ファスト映画のチャンネル運営者に対し、著作権侵害の疑いで刑事告訴を検討中だ。
これら企業は、著作者の同意なしにコンテンツを編集・要約した後、投稿したファスト映画が、著作権法上の複製権・転送権・2次的著作物の作成権に違反していると見ている。業界関係者は「単純な企業の利害関係の問題ではなく、コンテンツ制作のエコシステムを守るための象徴的な動きだ」と話した。
ファスト映画は1本の映画や複数回の分量のドラマシリーズを短く10~30分に、長いものは2時間以内に圧縮した映像コンテンツだ。ほとんどのファスト映画は著作権者の許可なく制作・投稿されている。視聴者数と再生回数を反映して策定された広告収益をファスト映画の制作者とYouTubeが分け合っている。再生回数はそのまま収益になるため、人気ドラマや映画を編集して投稿するチャンネルが後を絶たない。制作者は再生回数1回当たり、少なくとも3ウォン(約0.32円)、多い場合は8ウォン(約0.85円)程度の収益になるという。
ファスト映画関連の法的紛争が起こり、YouTubeについても議論が広がる見通しだ。Youtubeは「コンテンツID」など、著作権保護システムを運営しているが、実効性の議論が続いている。
原則として3回以上著作権侵害が確認されればチャンネルを削除しなければならないが、実際には6回以上申告されても維持されるケースが見られる。一部からは、YouTubeが広告収益構造を維持するため、大型チャンネルの違法映像の削除に消極的なのではとの批判も出ている。
捜査機関が利用者情報を求めても本社のサーバーが海外にあり、協力が円滑でない点も問題だ。実際、今年6月、韓国の主要放送局と制作会社が被害額数百億ウォン(数十億円)台と推算される、あるファスト映画チャンネルの運営者を著作権侵害の疑いで訴えたが、警察の情報開示の要請にGoogle(グーグル、YouTube)側は形式的な回答に終始し、捜査が遅れた。その後、YouTubeは映像を削除したが、違法に上げた収益は返金しなかった。
一方、日本は2022年に東京地方裁判所がファスト映画の制作者に5億円の損害賠償を命じ、一部の制作者に懲役刑を言い渡すなど、厳しい対応を取っている。
業界関係者は「日本の場合、ファスト映画に対する民事・刑事裁判の判決以降、警戒心が高まったが、Netflix(ネットフリックス)など、海外のオンライン動画サービス(OTT)のオリジナル作品は依然として無断で投稿されている」とし、「韓日の映像の権利者たちは『YouTubeに対し、共同で対応が必要だ』という点を確認しており、方策を議論している」と明らかにした。
<画像=ゲッティイメージ>