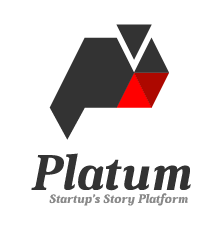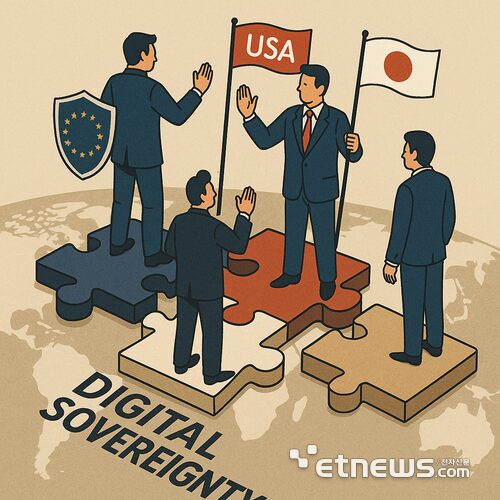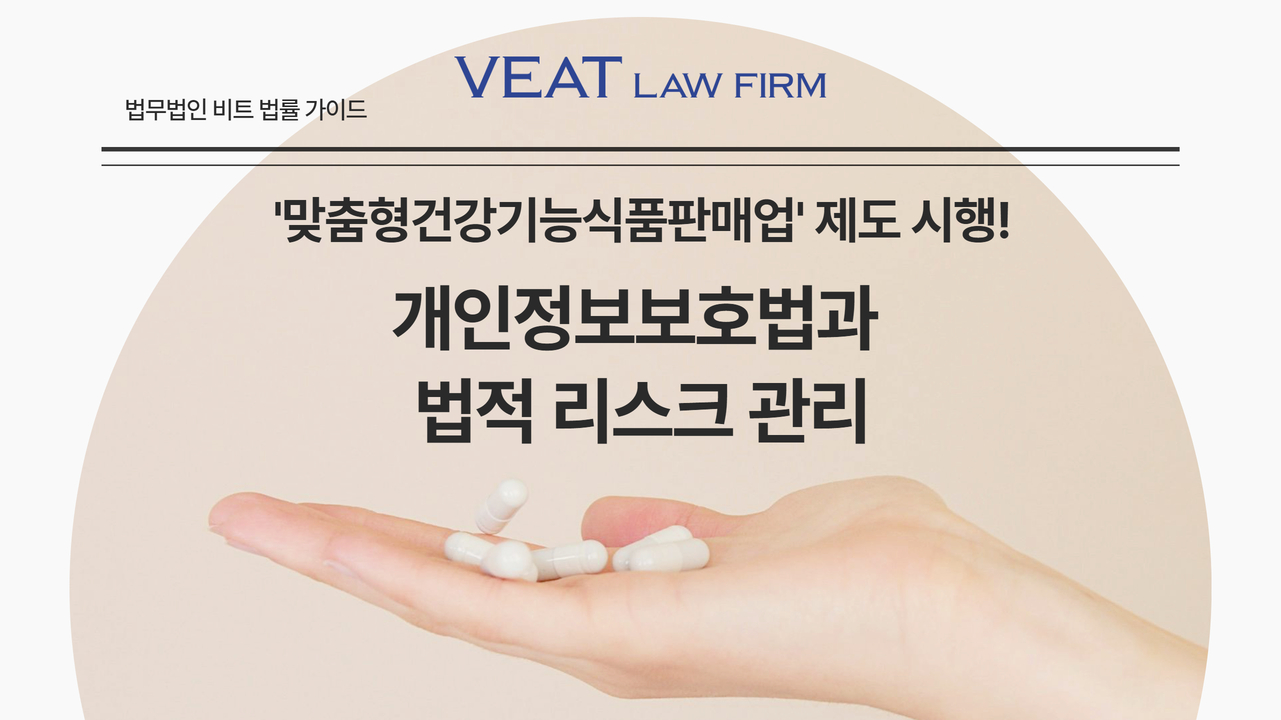- 良い意図を持った政策がどのように予想と正反対の結果を生み出したのか
- バタフライ効果よりも奇妙な政策の逆説
2025年7月22日、韓国で最も奇妙な政策実験の一つが静かに幕を下ろした。端通法(移動通信端末装置の流通構造の改善に関する法律)だ。
私たちがよく聞く「バタフライ効果」を思い出してみよう。ブラジルで蝶が羽ばたくと、テキサスに竜巻が起きり得ることを表現した言葉だ。ところが、端通法はこれよりも奇妙だった。善良な意図から始まった政策が反対方向に働いたのだ。
まるで北に行こうとコンパスを見て歩いたが、コンパスが逆になっていて南に行ってしまった形だ。
2014年、政策立案者たちはおそらくこう考えただろう。 「携帯電話市場は不公平だ。ある人は同じ電話を100万ウォン(約10万円)買い、ある人は50万ウォン(約5万円)で買う。このような価格の不平等をなくさなければならない。補助金を透明に公開して上限を決めれば、誰もが公正な価格で買えるはずだ!」。
これは典型的な「線形的思考」だった。Aという問題があるので、Bという解決策を適用すれば、Cという結果が出るという単純な因果関係を仮定したのだ。しかし市場は生きている生命体のようだ。1つの変数を操作すると、他の多くの変数が予期しない方法で反応する。
Complex System(複雑系)を研究する人々がよく言う言葉がある。 「システムを理解するには、木ではなく森を見なければならない」。端通法の立案者たちは「価格不平等」という木にのみ集中した。しかし、その木が「市場競争」、「消費者の選択権」、「流通業者の生き残り」などの他の木々とどのようにつながっているかは見過ごした。
経済学には「ゲーム理論」という興味深い分野がある。端通法をこの観点から見ると、その誤りが明確になる。
端通法ができる以前の市場は「競争ゲーム」だった。通信会社と流通業者は、互いにより良い条件を提示しようと競った。もちろんこの過程で「情報非対称」という問題があった。ある消費者はよい条件を見つけ、ある消費者はそうではなかった。
しかし、端通法はこの競争ゲームのルールを変えてしまった。補助金の上限を定めて公開を義務化すると、もう誰もより良い条件を提示することができなくなった。競争が消えると革新も消えた。
その結果、全ての消費者が「平等に」悪い条件を受けることになった。これは、まるで全ての学生が同じ点数を取るようにテストの満点を60点に制限するのと同じだ。 「ある学生は90点、ある学生は30点取るのは不公平だ!」という名分により、全ての学生を60点に合わせてしまった形だ。平等は達成したが、全体的な水準は落ちたわけだ。
システムの思考において重要な概念の一つが「フィードバックループ」だ。健全なフィードバックはシステムを改善するが、誤ったフィードバックは問題を悪化させる。
端通法は否定的なフィードバックループを作った。補助金の制限→競争の減少→消費者の不満の増加→陰性的取引の増加→より強い規制の要求→市場の更なる硬直化…このような悪循環が10年間繰り返された。
これはまるで体温が高いからといって体温計を冷蔵庫に入れておくのと同じだ。体温計は低い数値を示すが、実際の体の熱はそのままであるように、端通法も表面的には「透明性」を達成したが、実際の市場の問題は地下に隠されてしまった。
業界では端通法を「カモにされる人量産機」と呼び始めた。透明な情報公開を通じて消費者を保護するという趣旨とは異なり、むしろ消費者がより不利な条件で携帯電話を購入させられることになったためだ。
特に、中低価格の携帯端末機ユーザーが逆差別を受ける現象が現れた。テクノマートなどでは依然として特価販売が行われたが、一般消費者はこのような情報にアクセスしにくかった。結局、情報に明るい一部だけが恩恵を受ける仕組みがそのまま残り、支援金の総量だけ減った。
2020年代に入って「全国民が端通法の被害者」との表現が生まれるほど、否定的認識が広がった。市場の自律化を求める声が高まり、2023年から本格的な廃止論議がなされた。2024年に国会を通過し、2025年7月22日、正式に廃止に至った。
今、韓国の携帯電話市場は11年ぶりに自由競争体制に戻った。もちろん、新しい問題が生じることもある。高価格の料金制や長期約定による負担転嫁、過剰補助金による違約金などの懸念もある。
しかし、今回は過去の教訓をもとに、より賢く対応できるだろう。政府は市場モニタリングと事後管理体系を維持しつつ、市場の自律性は尊重する方向に近づいている。
端通法10年の最大の教訓はこれだ。複雑なシステムに介入するときは全体的な観点から接近しなければならず、意図しない結果に対しても常に開いた心を持たなければならないということだ。
科学で失敗した実験も大切なデータだ。端通法は失敗したが、その失敗から我々は大切な教訓を得た。良い意図だけでは良い結果を保証できないこと、そして複雑な世界では時に介入しないことが最善の介入になり得ることを。
ガリレオ・ガリレイが「それでも地球は回っている」と言ったように、我々も今、言うことができる。 「それでも市場は回っている」と。そしてそれが自然なことだと。